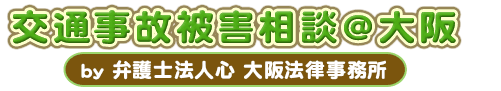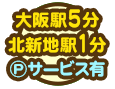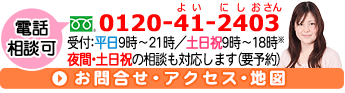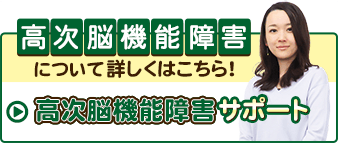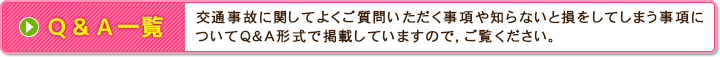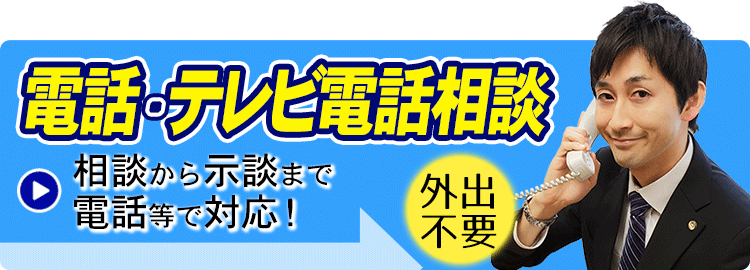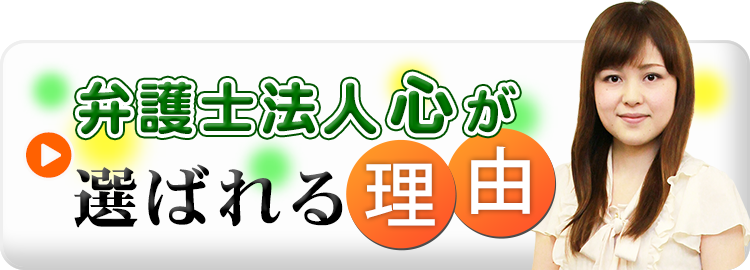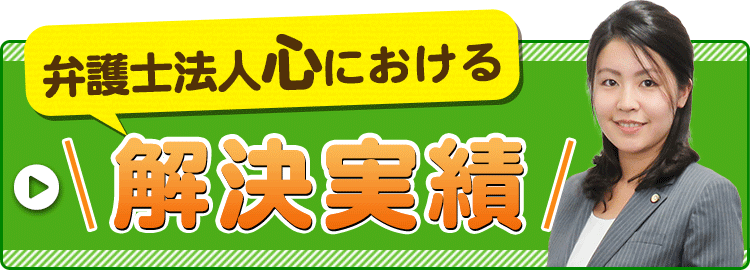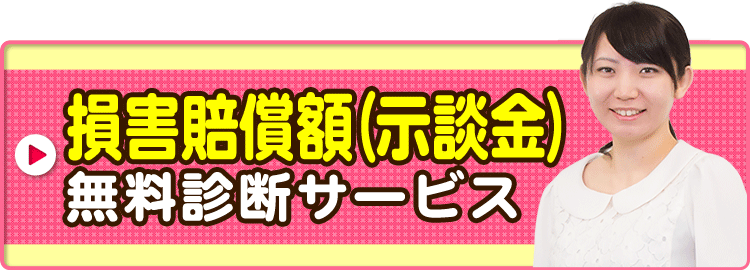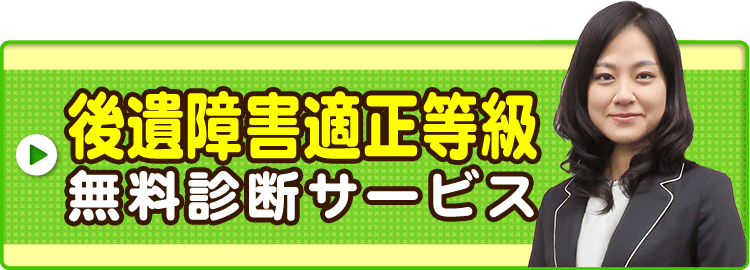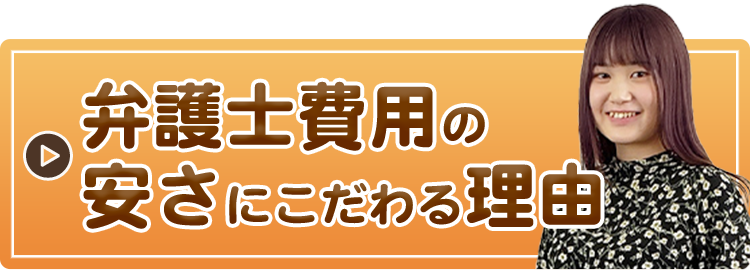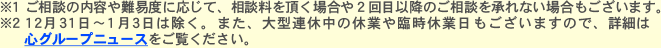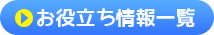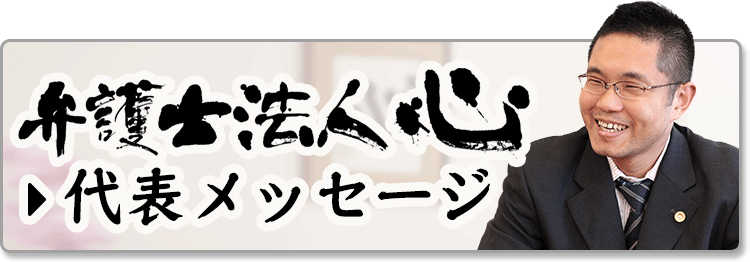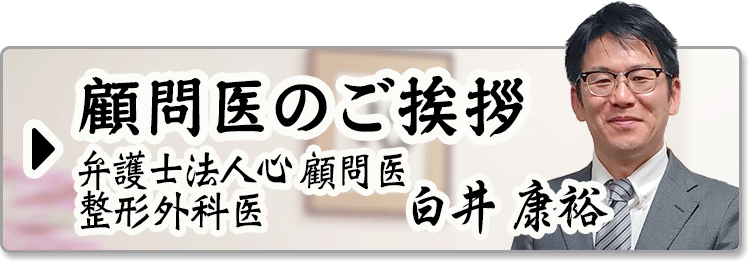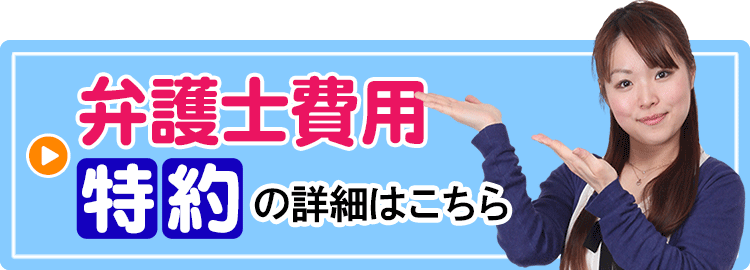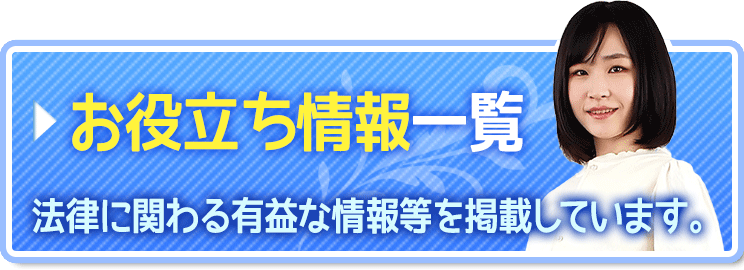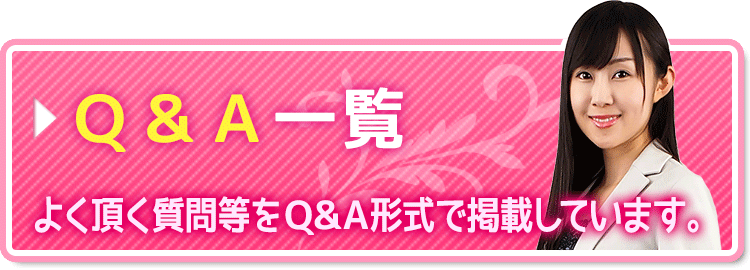高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

1 高次脳機能障害について
交通事故などで脳に損傷を受け、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きた状態を高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害は、その症状が多岐にわたること、全ての脳の機能が医学的に解明されていないこともあり、後遺障害等級認定や損害賠償額が問題になることが多い領域です。
そのような問題に適切に対応するためにも、高次脳機能障害については弁護士にご相談ください。
2 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料
高次脳機能障害として残ってしまった症状に対し、どのような後遺障害等級が認定されるかで後遺障害慰謝料の金額が変わります。
高次脳機能障害の等級には、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号といった種類があります。
例えば、3級3号であれば、いわゆる裁判基準(赤い本)では1990万円が後遺障害慰謝料の目安となりますし、9級10号であれば、裁判基準(赤い本)で690万円が後遺障害慰謝料の目安となります。
このように後遺障害慰謝料は、どのような等級が認定されたかで大きく金額が変わります。
また、慰謝料の額を算定する基準には自賠責基準や裁判基準などがあり、どの基準で算定したかでも大きく金額が変わります。
3 早期に弁護士へご相談を
自賠責保険において、高次脳機能障害が認められるためには、①脳損傷があること、②高次脳機能障害を疑わせる症状の存在、③同症状が脳損傷に起因することが必要です。
そして、自賠責保険においては、①脳損傷の有無で高次脳機能障害の該当性を判断し、その上で、②③脳損傷に起因する症状の内容によって、高次脳機能障害の等級の内、どの等級に該当するかを判断します。
そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、脳損傷を裏付ける適切な検査や、脳損傷に起因しどのような症状が生じているかの記録を早期から行うことが重要となります。
また、後遺障害慰謝料に関しても認定された等級に見合った慰謝料を受け取るためには、事故の相手方の保険会社との交渉が必要となる場合が多いです。
高次脳機能障害に詳しい弁護士であれば、これらについて適切なアドバイスをすることができますので、高次脳機能障害が疑われる場合は、早めに弁護士にご相談ください。
4 当法人は豊富な経験を有しています
当法人は、交通事故の案件を多く取り扱っており、高次脳機能障害についても豊富な経験があります。
また、後遺障害等級の適切な獲得のため、元自賠責調査事務所の職員や顧問医などと連携して対応しています。
取り扱った案件の一部を解決実績として当ホームページに掲載しておりますので、興味のある方はご覧いただければと思います。
交通事故に遭い、頭部を負傷された後、高次脳機能障害が残るのではないかとご不安な場合は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
交通事故を多く取り扱っている弁護士がご相談に乗らせていただきます。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
後遺障害が認定されるまでの期間 高次脳機能障害の画像所見について
高次脳機能障害に関して相談する弁護士の選び方
1 交通事故を多く取り扱っている弁護士を選ぶ

高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶ際には、まず交通事故を多く取り扱っている弁護士を選ぶことから始めると良いでしょう。
というのも、高次脳機能障害というのは、交通事故事件の中でも数が少ない障害の類型であるため、交通事故事件をあまり取り扱っていない弁護士であれば、高次脳機能障害の事件を扱ったことがないという可能性が十分に考えられます。
交通事故事件を多く取り扱っている弁護士であれば、当然高次脳機能障害の事件を取り扱っている可能性が高くなります。
また、法律事務所のホームページには、解決事例やコラムが掲載されていることが多いため、高次脳機能障害に関する事件を取り扱っているのか、どういった解決事例があるのかを実際に確認してみるのも良いでしょう。
2 医療部門のチームがある法律事務所を探す
高次脳機能障害は後遺障害の中でも極めて特殊な類型であり、通常の後遺障害申請で用いる資料とは異なる検査や医療記録等が必要となります。
そのため、高次脳機能障害を認定されるためには、どういった検査や医療記録等が必要であるのかが判断でき、実際の医療記録等から高次脳機能障害が認定されるのかどうかの見込みが分かる医療部門のチームがある法律事務所を探すと良いでしょう。
3 実際に相談を受けてみる
昨今では無料法律相談を行っている法律事務所も多いため、実際に相談を受けてみるというのは非常に有効な方法です。
なかなか法律相談を受けるというのはハードルが高いとは思いますが、お試し感覚でご相談いただいても問題ないかと思います。
やはり、最終的にこの弁護士に任せて良さそうか否かの判断は、実際にその弁護士と話をしてみるのが一番です。
その中で、自分にあった話し方や態度の弁護士であるのか、きちんと質問に答えられるような弁護士であるのか、高次脳機能障害の事件を経験したことがある弁護士であるのか、といったことを確認すると良いでしょう。
また、弁護士も多種多様であるため、様々な法律事務所で相談を受けてみることをお勧めいたします。
高次脳機能障害はいつ弁護士に相談するのがよいか
1 高次脳機能障害の相談はなるべくお早めに!

交通事故にあって高次脳機能障害が疑われる場合には、なるべく早くに弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
というのも、高次脳機能障害というのは、被害者本人に自覚がないケースが多いため、医師であっても高次脳機能障害を見逃してしまうこともあります。
そのため、高次脳機能障害を考慮しないまま示談を行ってしまい、本来得られた金額よりも少ない金額しか獲得できないといったケースが十分に考えられます。
上記のようなケースを回避するためにも、高次脳機能障害が疑われる場合には、早期に弁護士に相談した方が良いです。
2 高次脳機能障害が疑われる場合とは
高次脳機能障害は、脳の内部にある神経や血管が傷つくことによって生じるものですので、頭部に強い衝撃が加わることで発症するケースが多いです。
そのため、車で信号待ち中に追突され頭をハンドルに強く打ち付けてしまった場合やバイクから転倒して地面に頭を打ち付けたような場合には、高次脳機能障害が発症する可能性があるため、特に注意が必要になります。
3 高次脳機能障害を見逃さないためには
高次脳機能障害は、被害者本人が自覚することが難しいため、まずは事故後通院した病院の医師に頭を強く打ったことを伝え、しっかりとした検査をしていただくことが大切です。
また、高次脳機能障害の症状には、急に怒り出すなど情緒不安定になったり、いつもはできていた仕事や作業が急にできなくなったりといったものがあるので、被害者のご家族や友人が、被害者の言動や行動に普段と違う部分がないのか目を光らせておくことも非常に有効です。
4 高次脳機能障害での賠償請求は弁護士に任せた方が良い!
高次脳機能障害は、上記のとおり、そもそも発見することが難しく、高次脳機能障害と認められるためにも様々な資料が必要になります。
そのため、一般の方がご自身で資料を集め、後遺障害申請や相手方保険会社に請求していくのはかなりハードルが高いです。
弁護士に依頼すれば、的確な資料の収集や主張をすることができますので、高次脳機能障害の認定やそれに応じた賠償金を獲得することが期待できます。
高次脳機能障害が疑われる場合には、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
高次脳機能障害になった場合の示談交渉
1 まずは弁護士へご相談を

被害者側の過失が低いケースの高次脳機能障害案件は、裁判基準で算定した場合の適正な損害賠償金額が高額になります。
具体的な金額ですと、等級にもよりますが、数千万円以上となることも少なくありません。
ですが、これは弁護士が介入している場合にもらえる金額であって、弁護士が介入していない場合には、裁判基準よりも少ない金額での賠償額での示談となってしまいます。
2 示談交渉を弁護士に任せた場合
⑴ 後遺障害等級について
高次脳機能障害の等級については、相手方より、等級が高すぎると争われることも少なくありません。
争われた場合には、医学意見書等を用意するなどして、被害者の等級が適正な等級であることを主張立証していく必要がございます。
この点については、ご本人様だけでの交渉では限界があると思いますので、弁護士に任せていただくのが安心です。
⑵ 過失割合について
過失割合については、通常5%刻みで議論されますが、高次脳機能障害案件の賠償金が数千万円以上であることから、5%違うだけでも数百万円違うことになります。
過失割合を被害者有利にしていくためには、弁護士介入がほぼ必須といえます。
過失割合については、刑事記録を取り寄せて、事故発生状況を分析し、被害者側に有利な事情、加害者側に不利な事情がないかを検討していきます。
場合によっては、調査会社などに追加で調査を行ってもらい、被害者に有利な資料を作成してもらうこともあります。
これらの資料をもとに、過失割合について交渉していきます。
⑶ 賠償金額について
金額が大きい項目は、休業損害、後遺障害逸失利益、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、将来介護費などですが、これらの金額は、幅があります。
弁護士が介入しないと、適正な基準の裁判基準(弁護士基準)になることは難しいといえます。
また、争点はさまざまなものが予想されます。
将来介護費用の介護日額単価であったり、逸失利益の労働能力喪失率などが特に大きな争点となることが多いです。
示談前に弁護士のチェックを受けることをおすすめします。
高次脳機能障害についての弁護士への相談と裁判
1 弁護士に相談しても裁判にはならない

弁護士に相談すると裁判になり大変ではないかと不安に思っている方もいると思いますが、高次脳機能障害について弁護士に相談したからといって裁判になるわけではありませんので、ご安心ください。
以下では、高次脳機能障害について弁護士に相談してから解決までの一般的な流れについて簡単にご紹介いたします。
2 相談してから解決までの流れ
⑴ 弁護士に相談して依頼する
高次脳機能障害について弁護士に相談して、弁護士に高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請や交通事故の加害者側への賠償請求を頼みたいと思ったら、まずは、弁護士と委任契約を結びます。
弁護士に依頼する場合の費用は、弁護士費用特約を利用する場合は、保険で賄えることが多いです。
⑵ 後遺障害等級認定の申請を行う
高次脳機能障害について、治療を受けたものの後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。
弁護士に依頼している場合は、通院中の保険会社とのやり取りや後遺障害等級認定の申請のサポートは弁護士が行います。
⑶ 加害者側保険会社への賠償請求
後遺障害等級認定の申請により適切な等級認定を得た後は、加害者側への賠償請求を進めていきます。
弁護士に依頼している場合は、損害額の計算や保険会社との交渉は弁護士が行います。
賠償請求は、いきなり裁判を行うのではなく、加害者側の保険会社と合意できる金額があるか話し合いでの解決を試み、話し合いで解決できない場合に裁判を行います。
弁護士が依頼者の意思を確認せずに勝手に裁判を行うと決めることはなく、話し合いで解決するのか、裁判を行うのか依頼者の方の希望に従い進めていきます。
3 当法人へご相談ください
弁護士に相談すると裁判になるといったことはありませんので、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請や賠償請求についてご不安に思われていること等ございましたら、お気軽にご相談ください。
弁護士法人心 大阪法律事務所は、交通事故被害者の方がご相談いただきやすいよう交通事故の相談は原則無料としております。
高次脳機能障害における等級認定の申請の流れについて
1 症状固定日の検討

高次脳機能障害と診断され、後遺障害等級認定の申請を行う場合、まずは、症状固定に至っているのかを慎重に判断する必要があります。
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によっても到達すると認められる最終の状態に達したときをいう。」と定義されており、症状固定後の治療費は、原則、交通事故の相手方の賠償義務を負う範囲に含まれません。
2 自賠責保険後遺障害診断書の作成
症状固定に至っている場合は、病院で「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」に残存症状について記載してもらいましょう。
「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」の用紙は、保険会社や弁護士に依頼している場合は、弁護士から入手することができます。
3 その他資料の収集と申請書類の提出
高次脳機能障害等級認定の審査には、「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」以外に「日常生活状況報告書」や「神経系統の障害に関する医学的意見」などの書類の準備が必要となります。
提出すべき書類が準備できたら、書類を、交通事故の加害者が加入している自賠責保険会社に提出すると等級認定の審査がはじまります。
高次脳機能障害は、画像所見などにより、脳の器質的損傷の有無を判断し、日常生活状況報告書などの書類により、等級の種類が判断されます。
そのため、「日常生活状況報告書」や「神経系統の障害に関する医学的意見」に、高次脳機能障害によりどのような症状が残存しており、どのような支障があるのか適切に反映されていることが重要となります。
4 弁護士に相談を
自賠責保険は、提出された書面をもとに後遺障害等級認定の判断を行うため、高次脳機能障害について適切な等級の認定を得るためには、提出する書類に障害の内容が適切に反映されていることが重要となります。
当法人は、高次脳機能障害の等級認定の申請サポートに力を入れています。
高次脳機能障害と診断され、ご不安に思われている方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。